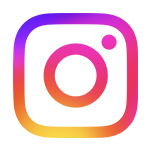しょうがいのある学生の避難訓練を実施
イベント
2023.10.06
9月26日(火)、4号館でしょうがい学生の避難訓練を行い、2名のしょうがいのある学生と14名の教職員・学生が参加しました。
これは地震や火災など避難が必要になった際に、しょうがいのある学生一人ひとりに合わせた避難方法を検討するもの。永留連太朗さん(社会福祉学科1年)と橋本昇汰さん(社会福祉学科2年)は、自身がもつしょうがいの特徴や注意事項、災害時の避難について記した個人避難計画書を事前に作成し、今回はそれに沿った方法で教職員や学生がサポートしながら避難訓練が行われました。
避難訓練の実施にあたり、講師を務めた尚絅大学の吉村千恵講師(専門:社会福祉学、障害学、地域研究)は、「訓練なので、安全を確保したうえで実施することが必要。災害発生時に初めて補助にあたる人でも理解できるようにしっかり記録しておくこと。最善の方法を検討するために補助してもらう側は怖いと思った瞬間を覚えておくこと」とアドバイスしました。避難訓練では、折り畳み式の担架であるベルカを使用して行われ、しょうがいのある学生を車いすからベルカに移し替え、2階から1階へ担いで移動。頭部、胴体、脚と3か所に計6名が配置され、声を掛け合いながら階段を下りました。
移動後は、意見交換会が行われ、補助にあたる人からは、「身長が同じくらいの人で胴体を支えれば身体が安定する」「動画で訓練の様子を撮影してQRコードからアクセスできるようにすればみんなが対応できる」などの意見が述べられ、補助をされた人からは「脚を支えてくれる人がいると安心感があった」「しょうがいの特徴を理解してもらえるとありがたい」などの意見が述べられました。
今後は、出された意見をもとに、個別の避難計画書を完成させる予定です。
これは地震や火災など避難が必要になった際に、しょうがいのある学生一人ひとりに合わせた避難方法を検討するもの。永留連太朗さん(社会福祉学科1年)と橋本昇汰さん(社会福祉学科2年)は、自身がもつしょうがいの特徴や注意事項、災害時の避難について記した個人避難計画書を事前に作成し、今回はそれに沿った方法で教職員や学生がサポートしながら避難訓練が行われました。
避難訓練の実施にあたり、講師を務めた尚絅大学の吉村千恵講師(専門:社会福祉学、障害学、地域研究)は、「訓練なので、安全を確保したうえで実施することが必要。災害発生時に初めて補助にあたる人でも理解できるようにしっかり記録しておくこと。最善の方法を検討するために補助してもらう側は怖いと思った瞬間を覚えておくこと」とアドバイスしました。避難訓練では、折り畳み式の担架であるベルカを使用して行われ、しょうがいのある学生を車いすからベルカに移し替え、2階から1階へ担いで移動。頭部、胴体、脚と3か所に計6名が配置され、声を掛け合いながら階段を下りました。
移動後は、意見交換会が行われ、補助にあたる人からは、「身長が同じくらいの人で胴体を支えれば身体が安定する」「動画で訓練の様子を撮影してQRコードからアクセスできるようにすればみんなが対応できる」などの意見が述べられ、補助をされた人からは「脚を支えてくれる人がいると安心感があった」「しょうがいの特徴を理解してもらえるとありがたい」などの意見が述べられました。
今後は、出された意見をもとに、個別の避難計画書を完成させる予定です。