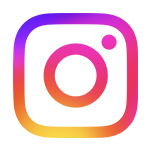FACULTIES
社会福祉学部

「現場主義」の学びから人に寄り添い支える福祉マインドを育てる
NEWSお知らせ
社会福祉学部
FACULTY OF SOCIAL WELFARE
社会福祉の専門知識と環境・地域などの社会共生の理念を融合し、 高い実践力を持つ福祉のプロを育てます
すべての人の幸せが実現できる社会を、環境から考える
2024年度より募集停止
「こどもまんなか社会」を支えるリーダーを育てます
福祉の心と身体活動・スポーツの視点から、 健康・生きがいづくりを考えます
多様な年代・経歴の人がともに学ぶ夜間部。 将来を見据えたキャリアアップを確実に実現します
[知の泉]
ケアの倫理が教えてくれること
「ケア(care)」という言葉は、昔は嘆く・泣くという意味で、ここから、心配しながら世話するという意味が生まれました。違うようで似た日本語「あつかう」は、「病気の熱(あつ)さで思いわずらう」という意味で、ここから「気づかいながら世話する」という意味が生まれました。現代人は「道具を扱う」といった平板化した意味しか知りません。けれど、私たちが生活のさまざまな場面で誰かのカラダやココロとふれあうとき、いつでも「あつかう」の古い意味にもふれているのかもしれません。私が翻訳したキャロル・ギリガンの「ケアの倫理」の本(写真)でも、ケアとは、誰もが弱く傷つきやすい私たちにとっての根源的な営みだと語ります。まだ自立・自律的人間観も強い現代において、ケアの倫理は、寄り添いあいながら生きることの意味を教えてくれます。さあ、ともに学びましょう!
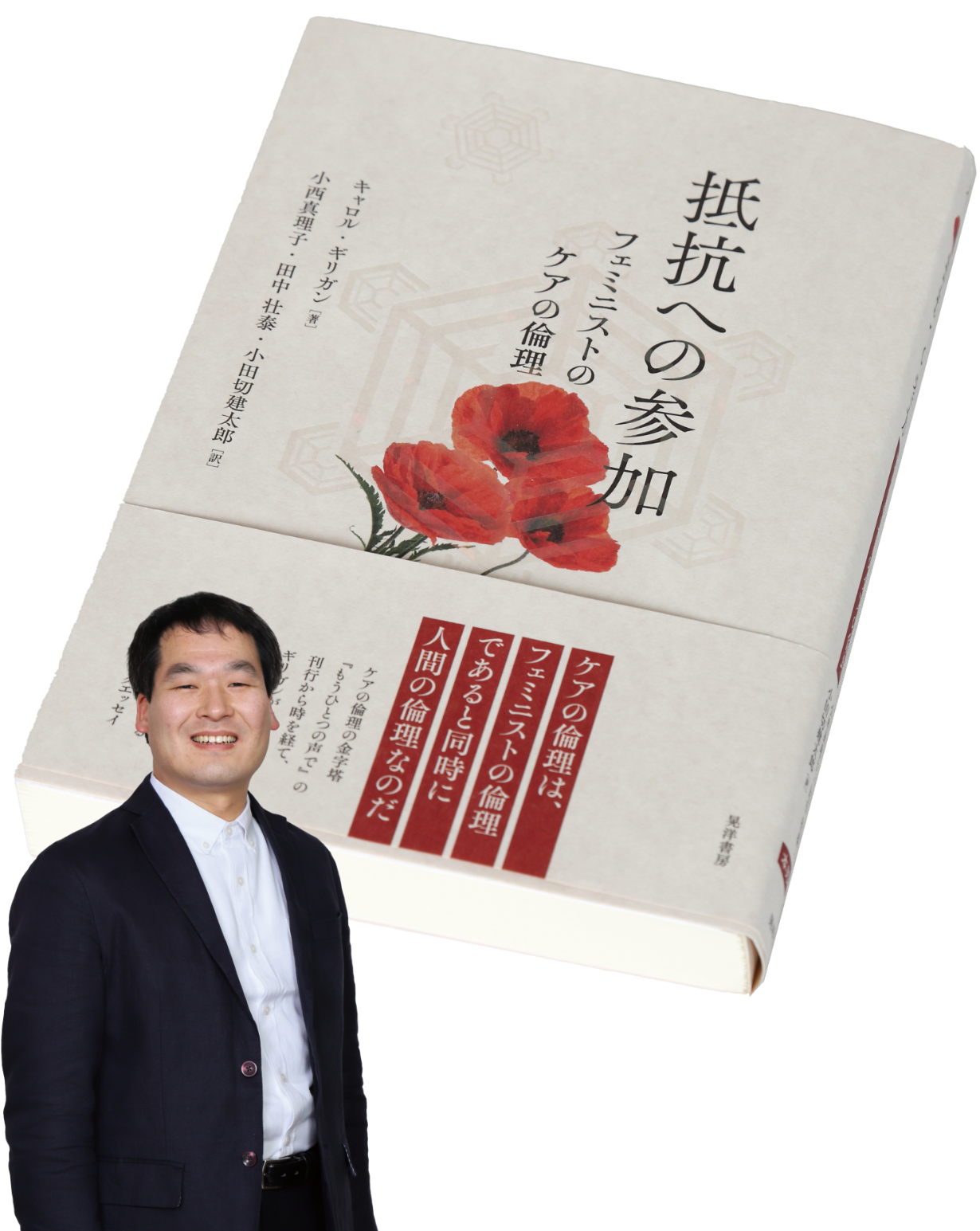
「令和6年能登半島地震」は、災害関連法制に「福祉」を取り入れる大きな転機になったことをご存知だろうか。第一部社会福祉学科では、地震や豪雨などの自然災害の被災地に出向いたり、公害の原点である水俣病を学ぶため、現地を訪れるなど、フィールドワークを教育の柱に捉えています。過去10年間、学生たちは「平成28年熊本地震」、「令和2年7月豪雨」、そして「令和6年能登半島地震」など、県内外の被災地に出向いています。活動のかたちは、ボランティアとして、またはソーシャルワーク専門職をめざす学生チームなどさまざまです。被災地では、秩序と混乱、複雑さと単純さ、専門職とボランティアが同時に存在する現実に触れ、普段の生活や身近な地域の課題を深く理解することができます。全国的にも類を見ない「災害×福祉」の学びは、危機と変化が常に発生し続ける混沌とした社会において新たな価値を創造するリーダーへとあなたを誘うでしょう。