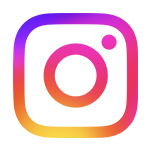第23期水俣学講義で自然科学研究機構生理学研究所の南部篤名誉教授が講演
2024.11.13
社会福祉学部の授業科目として開講されている第23期「水俣学講義」が始まりました。「水俣学講義」はオムニバス形式で、学内教員に加えて水俣病患者、学外の研究者、ジャーナリスト、医師、法律家などを講師に迎え、水俣病を単に知識として学ぶだけではなく、歴史や法、差別などさまざまな視点から水俣病を捉え、学びを深めるもの。水俣学研究センターホームページから、インターネット中継を通して一般の方にも公開され、この日は約120名の学生が受講しました。10月17日(木)、1173教室で行われた4回目の講義では、自然科学研究機構生理学研究所の南部篤名誉教授が登壇し、「神経生理学からみた水俣病」をテーマに、「自身がなぜ水俣病に興味関心を持ったのか」、「水俣病が神経におよぼす影響」などについて講義をしました。
南部氏は京都大学医学部を卒業後、京都大学医学部で助手として勤務、その後ニューヨーク大学へ留学。神経生理学を学び、脳深部にある大脳基底核を中心に、パーキンソン病やジストニアなどの運動疾患の病態生理について研究しています。水俣病に興味をもったきっかけとして南部氏は、「公害の原点であること」、「優れた芸術を生んでいること」、「さまざまな社会問題と交差していること」を挙げました。そのなかでも芸術について、「水俣病について触れている土本典昭氏や石牟礼道子氏の作品など、その表現はとても豊かであり、映像や文学としても美しく感動を呼ぶものが多い」と話しました。
また、「『水俣病』や『メチル水銀中毒』と聞くと、過去の病だとか既に終わった話という感じ方をする人も多いが、実際には研究自体は現在も進んでおり、過去にはわからなかったことが明らかになったりしている」と述べました。さらに、「水俣病の代表的な症状として手足のしびれ(感覚障害)があるが、手足の末端がしびれていることから末梢神経に原因があるとされてきた。しかし、末端を電気刺激して脳波を検査したところ、水俣病の方では中枢神経の反応がみられなかった。この他にもさまざまな検査をしてみると中枢神経に問題があるのではないかということがわかった。また、水銀を摂取する期間や、急性期・慢性期で症状やしょうがいが変化することも研究によってわかってきた。末梢神経は回復が可能なのに対し、中枢神経は回復が難しいため、手足のしびれという症状自体が軽かったとしても、回復させるのはなかなか難しいという現状がある」と説明しました。
最後に、南部氏は「水俣病の認定について、認定審査会というものがあるが、認定基準は厳しすぎる。患者達が求めている救済とは、健康な体を取り戻すことで、それが適わないからお金で補償するという構図になっている。水俣病で困っている人を取り残してはいけない。水俣病との関わりで個々の違いを認め一緒にできることを探すことや、人命や健康、自然環境など失ったものは取り戻せないことを学ぶことができる」と、講演を結びました。
福祉環境学科3年生の学生は、「神経学という視点から水俣病について学び、メチル水銀がどのように中枢神経に影響をおよぼしているのかなど、初めて聞いたのでとても勉強になりました。これからもっと学びを深めたい」と感想を述べました。