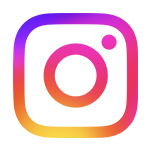地域モビリティ共創研究プロジェクトが「2024年度第2回公開勉強会」を開催しました
2025.03.11
2月10日(月)、14号館1411教室で「地域モビリティ共創研究プロジェクト」の2024年度第2回公開勉強会が開催され、研究者や自治体、企業関係者など、約40名が参加しました。これは、研究活動を推進し、公募から採択された先進的な研究テーマに挑戦する研究者グループを「高度学術研究プロジェクト」として支援する本学の研究プロジェクトです。今回の勉強会は、TaKuRooとEMoBIAの共催により、「『のるーと上熊本』(AIデマンドタクシー)の自動運転化に向けた協働のあり方」をテーマに実施され、地域の自動運転サービス導入に向けた課題や展望について意見が交わされました。勉強会の前に、参加者はJR上熊本駅前に集まり、「のるーと上熊本」のサービスエリアを実際に試乗するテクニカルツアーが行われました。
開会の挨拶で、溝上章志教授(専門:都市・交通政策、まちづくり、モビリティ)は「TaKuRooが始めた、予約状況に応じて最適な運航ルートを走行する乗合タクシー「のるーと上熊本」を試乗し、これをより高度で利便性の高いシステムにするにはどうしたら良いかを関係者で考えるために今回の勉強会を計画しました。今後、自動運転化が進むことで、人件費の削減が期待でき、利便性だけでなく運行効率性も高める今後の展開が楽しみです」と述べました。続けて、「のるーと上熊本」の概要やビジネスモデルを説明し、「現在、TaKuRooは『のるーと上熊本』の自動運転化に向けて営業運行を行っています。すでにオンデマンド乗合システムも導入し、さらに民間企業や自治体、他の交通機関と連携を進めることによってより実現可能な自動運転システムとなりうることが、他の自動運転化プロジェクトに対する優位性と言えます」と述べました。
続いて、名古屋大学未来社会創造機構モビリティ社会研究所の金森亮特任教授が「高蔵寺ニュータウンにおけるオンデマンド型自動運転サービスの紹介」と題して、オンデマンド型自動運転サービスの導入事例について紹介しました。自治体と連携しながら自動運転を活用した公共ライドシェアを実装した経緯や、その事業モデルについて詳しく解説。今年度実施された車掌ロボットや遠隔アシストの実証実験についても触れ、今後の発展可能性について言及しました。
さらに、名古屋大学未来社会創造機構モビリティ社会研究所の赤木康宏特任教授がオンラインで登壇し、「自動運転サービスの現状と見通し」について講演しました。国内外の自動運転事例を紹介し、名古屋大学で進行中の自動運転車開発や高蔵寺ニュータウンでの自動運転システム「ADENU」の実用化事例を紹介しました。また、遠隔アシスト運転の実証実験にも言及し、運転手不足解消に向けた技術発展の必要性について解説しました。
勉強会終了後には、本館4階のグリルにて懇親会が開催され、自動運転技術の未来や、地域におけるモビリティの課題について参加者同士が意見を交換しました。