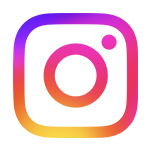2024年度能登半島地震・能登半島豪雨災害の被災地支援活動
2025.03.28
3月20日(木)から23日(日)にかけて、本学学生3名(第一部社会福祉学科1名、子ども家庭福祉学科2名)と社会福祉学部の黒木邦弘教授(専門:ソーシャルワーク方法論)・栗原武志准教授(専門:体育科教育学)が能登豪雨災害ボランティアに従事しました。本学の参加は、10月、11月、12月に続く第4弾で、全国から35名の学生がボランティアに参加しました。この取り組みは、「D-WAS」(Disaster Welfare Assistance Students)と呼ばれ、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟が企画・実施しています。
活動初日、本学・立命館大学・龍谷大学の合同チームは、輪島市田村区の稲作再開にむけて、田んぼの用水路の泥出しを行いました。区長からは、「田村区80名程度の住民のなかで、用水路の泥出しを担える若手高齢者は数名程度。学生ボランティアが入るのは初めてでありがたい」と、感謝の言葉をいただきました。また、昼食時には、集会所やビニールハウスの避難の様子や、田村区の存続に向けた想いを伺うことができました。
活動2日目、D-WASに加えて、神戸大学など他大学や地元住民なども加わり、輪島市深見区の海岸清掃を行いました。9月の豪雨によって漁具や木材が海岸に埋まっているため、ショベルカーによる重機作業、漁具や材木などを掘り起こす手作業によって海岸の再生を進めました。本学は、漁業用の網の掘り出しを重点的に行いました。
活動3日目、前日に地元の方から輪島市で有名な朝市が出張朝市として再開していると情報を受け、輪島市中心部の復旧状況と出張輪島朝市の様子を視察しました。現地では、昨年3月に輪島市役所を調査した黒木教授が、発災後の朝市を含む輪島市内の様子について学生たちに説明しました。出張輪島朝市は、10時から13時ごろまで営業しており、輪島塗のお箸や器、乾物など20軒ほどが店開きをしていました。学生たちは、買い物を兼ねてお店の方と交流しました。