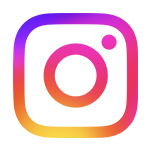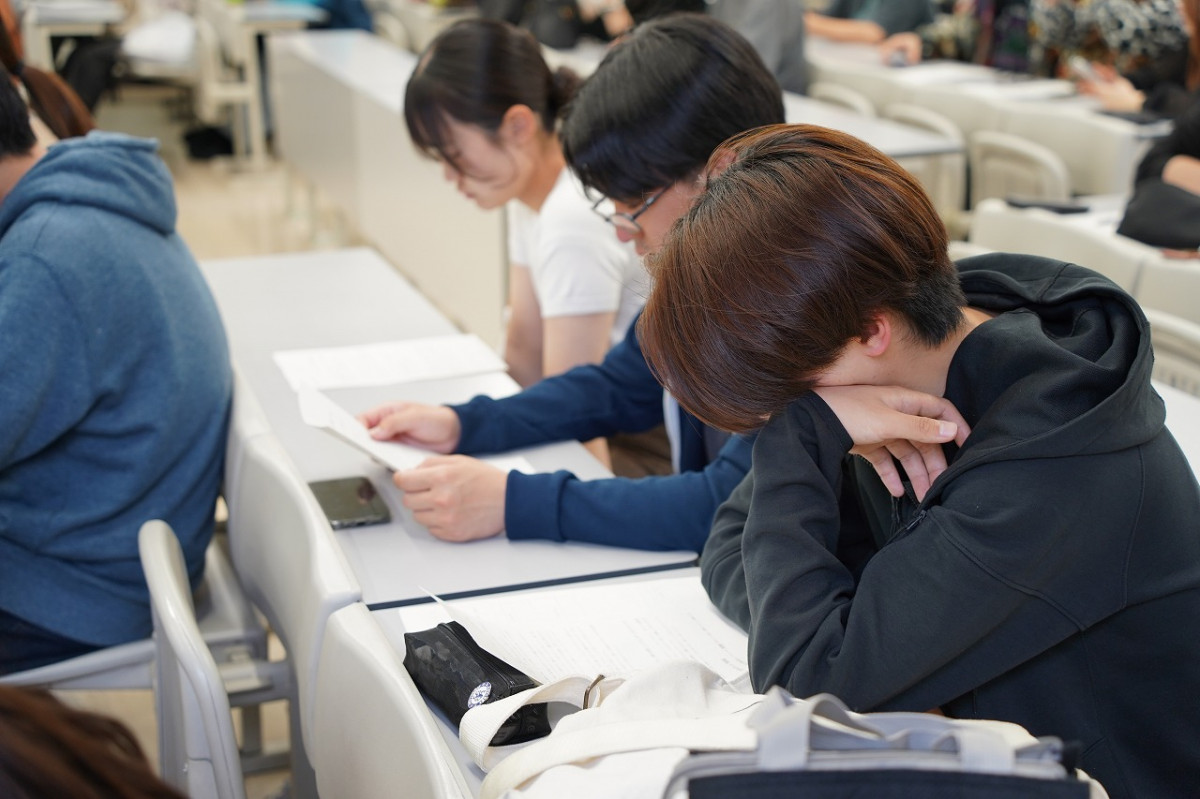飲酒事故防止講演会を実施しました
2025.05.09
4月30日(水)、第一部学生自治会厚生委員会主催の「飲酒事故防止講演会」が4号館427教室で開催され、約110名の学生が参加しました。本講演会は、飲酒に関する正しい知識とその危険性を学生に伝え、飲酒事故を未然に防ぐことを目的として、同委員会が毎年実施しているものです。
はじめに、吉川勝広学生部長が「各サークルに新入生が加わり、新歓コンパも増える時期かと思います。皆さんはすでに成人として、自覚ある行動が求められます。本日の講演を通じて、事故防止に努めていただきたい」と挨拶しました。
続いて、学生課の北原かおり氏が登壇し、飲酒事故をどのように防ぐかについて講演を行いました。北原氏は学生支援の立場から、大学生が正しい知識を持って飲酒と向き合うことの重要性を強調。多くの学生が20歳を迎えて飲酒可能となる一方、アルコールの危険性について十分な教育が行き届いていない現状を指摘しました。講演では、「お酒は時に命を奪うもの」と明言し、全国で実際に起きている大学生の飲酒事故の深刻さを紹介。飲酒事故により命を落とした大学生の遺族による寄稿文を配布し、学生にその内容を熟読するよう促しました。急性アルコール中毒による死亡事故は、一気飲みなどによる短時間での大量摂取が原因で、2004年以降の15年間で少なくとも32名の大学生が命を落としていると説明。「誰もが被害者にも加害者にもなり得る」と、強く訴えました。
また、「酔いつぶれた人を救う4つのチャンス」として、「①イッキはさせない・酔いつぶさせない、②酔いつぶれた人を絶対に一人にしない、③横向きで自然に吐かせる、④おかしいと思ったら、ためらわず救急車を呼ぶ」という行動指針を紹介。
さらに、アルコールの分解能力には個人差があることに触れ、「アルコールパッチテストを通じて自分の体質を知る機会を提供している」と本学の取り組みを説明。6月以降、本学ポータルサイトを通じて保健室より案内を行い、サークルなど少人数グループでの受検も推奨していると述べました。
講演の最後には、飲酒による身体的健康被害についても言及。20代では脳の発達が完全には終わっておらず、大量の飲酒が脳機能の低下を招くという研究結果や、アルコール性肝炎・肝硬変・出血性胃炎・骨粗鬆症など多岐にわたる疾患のリスク、さらには生活習慣病との関連性についても説明がなされました。
講演を受け、厚生委員会理事長の中原頌太さん(経済学科4年)は「今回の講演をとおして、飲酒事故の恐ろしさは十分に伝わったと思います。これから新入生歓迎コンパなどもあると思いますが、大きな事故はもちろん、軽微な事故も未然に防げるよう、お酒と正しく向き合っていきましょう」と語りました。