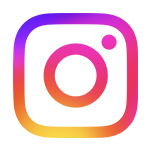令和7年度 春期公開講座がスタート
2025.07.01
6月21日(土)、「新1号館 みらい」121教室/131教室で令和7年度春期公開講座が開講し、保育関係者や学生、一般の方など約60名が参加しました。今期の講座は、「子どもの物語をつむぐ保育」をテーマに、本日と7月12日(土)の全2日間。保育の暮らしのなかにある、子どもたちの日々の営みや成長の物語に焦点を当て、保育の本質を見つめ直すことを目的としています。ワークショップや講義をとおして、子どもの遊びと暮らし、日々の情報発信、小学校との接続についても考えていきます。
はじめに、公開講座運営委員長の圡井浩嗣教授が「近年、ICTやAIの進展により保育現場も大きく変化し、効率化や可視化が進む一方で、人間らしさが後回しにされているような不安もあります。今回のテーマには、子どもの成長を一つの大切な『物語』として見つめ直そうという想いが込められています。本講座をとおして、子どもに寄り添った保育について考え、参加者同士が語り合える場となれば幸いです」と挨拶しました。
講座では、上原真幸准教授(専門:保育・児童家庭福祉)が登壇し、「保育における『教育』とは、教え込むことではなく、子どもが自らの遊びをとおして学ぶことを意味します。保育者は子どもの経験や環境に応じて、遊びを支え、広げる『遊びのプロ』である必要があります。子どもの成長を支える遊びをどう創り出すかが、保育の大切な役割です」と語りました。続くワークショップ「参加者による『子どもの遊び』体験」では、受講者が11グループに分かれ、全力で約6500個の紙コップを使って「遊び」を展開。塔を建てたり、椅子や城を作ったりと全力で遊ぶなかで、自然と交流が深まっていきました。上原准教授は、実際の保育現場での子どもの様子も取り上げながら、すべての子どもが遊びを共有できる環境を整える保育者の役割について解説しました。
後半は、「相手に伝わる記録づくり」をテーマに、午前中の遊びの様子を記録としてまとめる活動が行われました。参加者は、「誰が読んでも分かる・伝わる」記録をめざし、写真やレイアウトに工夫を凝らした記録づくりに取り組みました。完成後はグループで記録を共有し、工夫した点や難しかった点、他者の記録の優れている点について語り合いました。また、他園のおたよりの事例や、SNS・アプリなどの情報発信ツールの活用方法、保護者への伝え方などについても意見交換が行われました。
最後に上原准教授は、記録づくりにおいて大切な視点として「言葉選び」の重要性を強調しました。「言葉の受け取り方は人それぞれ。誤解を生まない表現や、否定形をできるだけ避けることが大切です」と述べたうえで、『おたより』をあまり読んでもらえない保護者の事例を挙げ、「嬉しくなる内容や伝え方を工夫することで、“また読みたい”と思ってもらえるようになる」と話しました。上原准教授は、「記録づくりも『楽しむ』ことが大切です」と締めくくり、参加者にとって記録の意義や伝え方を深く考える機会となりました。
受講した保育関係者の男性は、「紙コップを使った遊びのアイデアだけでなく、情報配信についてもグループ内で他の参加者の話を聞くことができ、さまざまなやり方や考え方に触れることができました。自園の取り組みを見直すきっかけになったと思います」と感想を語りました。