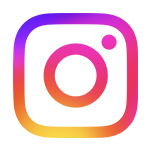第一部社会福祉学科の学生が災害時における福祉避難所の開設を模擬体験
2025.05.19
5月10日(土)、熊本県玉名郡和水町にある社会福祉法人青いりんごの会「銀河ステーション」で、社会福祉学部の学生が災害時における福祉避難所開設の模擬訓練を行いました。この訓練は、第一部社会福祉学科社会共生コースの授業「社会共生演習(災害と社会フィールドワーク)」の一環として行われたもので、災害時を想定し、要援護者支援に必要な福祉避難所の開設・運営の流れを学ぶことを目的としています。訓練には、同コース2年生6名と福祉環境学科3年生2名の計8名の学生が参加しました。
本訓練は、災害派遣福祉チーム(DWAT※1)を支援する学生チーム「DWAS※2」が発災時に参集し、現地に赴いて福祉避難所を開設するという、熊本県内では初めての試み。指導には授業を担当する黒木邦弘社会福祉学部教授(専門:ソーシャルワーク方法論)、社会福祉法人リデルライトホームの職員4名があたり、「銀河ステーション」の森光靖施設長を含む職員2名、そして要支援者役の当事者3名が協力しました。
訓練に先立ち、事前学習を行い、訓練当日は「長洲地域で最大震度7の地震が発生した」という想定のもと実施。熊本市内3か所から支援物資を搬送するという設定で、移動中にはZoomやドローンを活用し、現地・車両・本部間で道路状況や被災情報を共有する訓練を行い、学生たちは情報伝達の重要性を実践で学びました。
到着後は15分間でパーテーションを設置し、4床分の福祉避難所を立ち上げる訓練を実施。これは、被災者を迅速に受け入れる体制を整えたうえで、行政へ報告するという次のステップへつなげるための重要なプロセスで、学生たちは事前学習の成果をいかして時間内に作業を完了しました。
避難所の設営後は、要援護者役の3名に対してアセスメントシートを手に模擬聞き取りを実施。リデルライトホーム生活相談員の米田正人氏は「質問を重ねると、要援護者も疲弊します。対話を通じて相手の情報を自然に引き出すことが大切です」と助言しました。
続いて、災害時の車中泊仕様の車両を見学。米田氏が集団避難が困難な人々の車中泊という選択肢と、そこに寄り添う福祉避難所の役割について説明しました。熊本地震で車中泊を経験した学生もおり、自身の体験と重ねながら学びを深めていました。
また、ドローンを用いて周囲の状況を確認する訓練では、リデルライトホーム事務次長の古賀友規氏の操縦により災害時の利便性を体感。さらに、防災・安心プランナー(防災士)の柳原志保氏(しほママ)によるワークショップも開催され、支援学校の生徒や保護者とともに防災トイレの設置・撤収を体験しました。
緒方結衣さん(第一部社会福祉学科2年)は「移動中に連絡を取り合うなかで、道路状況を共有することの重要性を学びました。聞き取りでは、短時間の対話から必要な情報を引き出すことの難しさを実感しました。災害が起こった際の福祉支援について、大学の授業の一環として参加でき、とても貴重な機会になりました」と振り返りました。
古賀氏は「事前学習の成果もあり、避難所の設営において学生たちは自発的に動いてくれ、その姿勢に感心しています。聞き取りが初めての学生も多かったと思いますが、今回の経験を今後の実習や活動にいかしてほしい」と期待を寄せました。
※1...大規模災害時に、被災自治体からの要請を受け、避難所等において高齢者や障害のある人など、要配慮者に対する福祉支援を行うために、さまざまな職種の福祉人材で構成された災害派遣福祉チーム
※2...Disaster Welfare Assistance Studentsの略、災害時の福祉支援に取り組む学生たちという意味